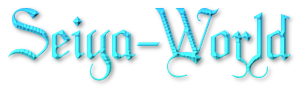はじめに
どうもSeiyaです!皆さんは量子力学について興味ありますか?量子力学って言葉が既にワクワクしますが、次元とかいう概念がこの分野に属しています。ワクワクが止まりません。
量子
1690年 : クリスティアン・ホイヘンスは本を出版。光の回折や干渉といった現象を波の性質を用いて説明できるので光は波動であるという説。
1704年 : アイザック・ニュートンは本を出版。ニュートンは光が直進する性質や反射屈折する性質から光を粒子の流れと見なせるため光は粒子であるという説。
1805年 : トーマス・ヤングが画期的な実験二重スリット実験と呼ばれる実験を行う
実験設計: 光を出すライト、その奥に2つのスリットを開けた壁、さらに奥に光に反応して色がつくスクリーンを設置する。
干渉模様: スリットを通過した2つの光の波が重なることで、シマシマ模様(干渉模様)が発生する。これは2つの波の重なり合いによって生じる。
光の波動説: ヤングの二重スリット実験(1805年)は、光が波動であることを示す重要な実験でした。二重スリットを通過した光の干渉模様によって、光の波動性が証明されました。
出力を絞った実験: 1982年、浜松ホトニクスが光の出力を極限まで絞って同じ実験を行いました。光が波であるとすれば、出力を弱めても干渉模様が現れるはずでした。
実験結果: しかし、実際の実験ではスクリーンに干渉模様ではなく点々が現れました。これは波動説に衝撃を与えました。
光の性質の混乱: 光が波であれば、どんなに弱い光でも干渉模様が出るはずで、ポツポツと点がつく結果は説明できません。光が粒子であると考える方が、この現象を理解するのに適しているように見えます。
継続実験: 弱い光を当て続ける実験では、点の数が増え、ランダムに見えるが、最終的に干渉模様を形成しました。
新たな仮説: 干渉模様は波の重なり合いによるもので、粒子説では説明できません。ヤングの実験は光が波であることを示しましたが、弱い光で点が現れることは粒子説を支持します。
波と粒子の矛盾: 光が粒子であれば、粒子がスリットを通ってスクリーンにぶつかり跡が残ると解釈できます。しかし、粒子が打ち続けられた場合に干渉模様が形成される点は説明できません。波は両方のスリットを通るからこそ干渉が起こるので、粒子が2つのスリットを同時に通ることは考えにくいです。
二元論の困難: 光の実験結果を単純に粒子または波動として説明するのは難しく、一粒一粒は粒子であるにもかかわらず、最終的に波の干渉模様と同じ結果になることは直感に反します。
波動-粒子二重性: 光はライトから放たれると波として空間を進み、二重スリットを波として通り抜けることで干渉が起こり、スクリーンにぶつかる瞬間に粒に変わると考えられます。
センサー付きの実験: スリットAとスリットBに光が通ったらお知らせするセンサーを設置し、どちらのスリットを光が通ったかを確認する。
実験結果: センサーは必ずどちらか片方しか反応せず、同時に反応することはありませんでした。
干渉模様の消失: スクリーンに浮かび上がった模様には、干渉模様が消え、波としての性質が見られなくなりました。
光の粒子性と波動性の変化: 光がどちらのスリットを通ったかを確認するだけで、光の波動的な振る舞いが消え、粒子として振る舞うようになります。センサーを外すと、再び干渉模様が現れます。
波と粒子の二重性: 光はライトから放たれると波として空間を進み、二重スリットを波として通り抜けます。しかし、センサーがある場合、観測された瞬間に粒に変わり、スクリーンにぶつかります。
直感との矛盾: 一般的な直感には反しますが、事実としてこうした現象が観測されているため、受け入れざるを得ません。
光の波動・粒子二元論の限界: 光が波動であるか粒子であるかのシンプルな考え方が成立しないことがわかります。
量子力学への関係: 光が波動と粒子の両方の性質を持つことから、量子力学の基本的な概念が生まれました。
量子という単語の由来: 科学は事実から法則を作り上げ、それを実験で確認する作業です。1800年代後半に物理学では説明できない現象(物体に熱を加えると光り出す)がありました。例として、金属を加熱すると赤く光る現象が挙げられます。
身近な例: 火山噴火やオーブントースター、ヒーターなどで熱を加えた物体が赤く光る現象があります。これは黒体放射と呼ばれ、温度によって発光色が決まっています。
黒体放射の法則の難しさ: 物理学者たちは、何度で何色に光るのかを説明しようと試みましたが、一部しか説明できず、全てを説明する法則を既存の物理学からは導けませんでした。
プランクの仮説: 1900年、マックス・プランクがエネルギーが飛び飛びの値しか取らないという仮説を立て、プランクの法則を導きました。この法則により、黒体放射の周波数分布を予測した結果が実験結果と完璧に一致しました。
整数仮説: プランクの仮説において、nは整数であり、h は定数です。これによりエネルギーEは飛び飛びの値しか取らず、連続的ではなく非連続的(離散的)であることが示されています。例えば、Eは0、hν、2hν、3hνといった値しか取らず、間の値は存在しません。
直感に反する現象: 物理学的現象は連続的であると考えられていたため、この非連続的な仮説は感覚的に受け入れがたいものでした。たとえば、水の温度が10度単位しか取らないと考えると、直感に反するように感じられます。
非連続的なエネルギー: 水の温度を例にすると、10度から20度まで飛び飛びに変わるような感覚で、エネルギーが連続的でなく飛び飛びであることが示されています。このことは直感に反しますが、プランクの仮説により、黒体放射が完璧に予測できるようになります。
プランクの仮定: プランクはエネルギーが最小単位($$ hν $$)として飛び飛びの値しか取らないことを仮定しました。エネルギー $$ E $$ は、$$ 0、hν、2hν、3hν $$ という飛び飛びの値を取ります。
量子の概念: この最小単位のエネルギーを「量子(Quantum)」と呼びます。Quantumはラテン語から来ており、「どのくらいの」という意味があります。
量子の概念: 量の最小単位を量子(Quantum)と呼び、エネルギーが量子単位で飛び飛びの値を取るという仮説をエネルギー量子仮説と名付けました。
プランク定数: プランクの仮説に基づき、エネルギーの飛び飛びの値を説明するために導入された定数 $$h$$ は、6.6×10^-34 という値で定義され、プランク定数として重要な定数となりました。
量子力学の始まり: プランクの仮説により、黒体放射が説明可能になり、量子力学の基礎が築かれました。当時は大した意味がなさそうに見えましたが、現在では重要な法則とされています。
アインシュタインの発展: 1905年、アルベルト・アインシュタインがこの量子の概念をさらに発展させ、当時の物理学で説明できなかった光電効果という現象を説明しました。
光電効果の発見: 1800年代に見つかった現象で、金属に光を当てると電子が放出されることが観測されました。
光電効果の法則:
- 一定以上の振動数の光でなければ電子の放出は起こらない。
- 光の強度を上げると放出される電子の数は増加するが、電子のエネルギーは変わらない。
- 光を照射した瞬間に電子が放出される。
光の波動説の問題:
- 当時、光は電磁波(波)であると考えられていましたが、光が波であれば、低い振動数の光を長時間当て続ければ電子放出に必要なエネルギーが溜まるはず。
- 光の強度を上げると放出される電子のエネルギーが増加するはずですが、実験結果はそれを示しませんでした。
アインシュタインの量子化の概念: アインシュタインは、プランクが考えた量子化の概念を光にも適用しました。光はhνというエネルギーを持った粒子(光子)の集合体であり、エネルギーEは $$E = nhν$$ と表されます。
光電効果の説明: この考え方により、光電効果の実験結果をすべて説明できました。
- 一定以上の振動数の光でなければ電子の放出が起こらない理由は、光子一粒のエネルギーが振動数によって決まるためです。
- 光の強度を上げると放出される電子の数は増加するが、電子のエネルギーは変わらない理由は、光の強度を上げても光子の数が増えるだけであり、光子一粒が持つエネルギーは変わらないためです。
光電効果の説明: 光を照射した瞬間に電子が放出されるのは、光子が粒として金属に衝突し、即座にエネルギーが電子に伝わるためです。アインシュタインは光を量子化された粒(光子)と仮定し、光電効果の実験結果を完璧に説明しました。
プランク定数の一致: 光電効果の実験結果から計算されたプランク定数 $$ h $$ は、プランクが黒体放射を説明する際に設定した $$ 6.6×10^{-34} $$ とぴったり一致しました。これは、偶然にしてはできすぎており、量子化という考え方が何かの本質を捉えていることを示唆しています。
量子化の本質: 黒体放射と光電効果という全く異なる実験結果において、同じプランク定数が導かれることから、量子化の概念が重要であることがわかります。
アインシュタインの功績: アインシュタインはこの功績によりノーベル賞を受賞しました。
発光スペクトルの説明: 発光スペクトルは、光を分解してその波長ごとに色を分けたものです。虹の現象もこの一例で、太陽の光が空気中の水分によって分解され、青色から赤色までの様々な色が見えます。
電磁波の性質: 光の正体は電磁波であり、太陽から届く電磁波は様々な波長が混じり合っています。人間の目で見える電磁波の範囲はおおよそ400nmから800nmです。
分光器の利用: 電磁波を波長ごとに分解する装置を分光器と呼びます。分光器を使って太陽を覗くと、美しい虹色の発光スペクトルが見えます。
蛍光灯と発光スペクトル: 蛍光灯の光を分光器で見ると、特定の波長の光しか出ていないことがわかります。蛍光灯の管の中に入っているガスの種類によって発光する波長が異なります。この現象を発光スペクトルと呼びます。
水素ガスの発光スペクトル: 水素ガスに電気を流すと、特定の波長の光が見えます。これも発光スペクトルの一例です。
ボーアの仮説: 物理学者のニールス・ボーアは、水素原子の構造を考え、原子内の電子が特定の飛び飛びの軌道にしか存在できないという仮定を立てました。これは電子の軌道を量子化するという考え方です。
量子数: ボーアは電子の軌道を表すために量子数$$ n $$を導入しました。
量子化された電子軌道: ボーアは、電子が特定の飛び飛びの軌道にしか存在できないと仮定しました。これにより、電子のエネルギーも量子化されます。
光子の放出: ある軌道の電子が別の軌道に移る際、そのエネルギー差が一個の光子として放出されます。これがボーアモデルと呼ばれます。
水素の発光スペクトルの説明: ボーアモデルを用いると、水素の発光スペクトルが完璧に説明できました。電子の軌道間のエネルギー差を計算すると、水素スペクトル線の波長と一致します。
不可視のスペクトル線: 水素スペクトルは目に見える4本の線だけでなく、目に見えない波長の部分にもいくつかの線があり、ボーアモデルはそれらも完璧に説明しました。
ボーアの業績: これらの発見により、ニールス・ボーアはノーベル賞を受賞しました。
ボーアモデルの重要性: ボーアモデルは現在では正確なモデルではありませんが、原子を量子力学的に考えた初めての例として非常に有名です。
量子化のアイデア: プランク、アインシュタイン、ボーアらが量子化というアイデアを使って、従来の物理学で説明できなかった現象を解明しました。連続的ではなく飛び飛び(離散的)になっている量子化のアイデアは、常識を覆すものでした。
量子化の本質: 量子化の発想により、3つの謎(黒体放射、光電効果、水素の発光スペクトル)が解明され、このアイデアが本質を捉えていることが明らかになりました。
波動関数
光の二重性: アインシュタインが光を量子化して考える前は、光は波であると考えられていましたが、光を量子化した粒子(光子)として考えると説明できる現象も存在します。光は波としても粒子としても説明できない現象もあるため、光は波動性と粒子性の二重性を持っていると理解する必要があります。
新たな物理学の必要性: 光が波動性と粒子性の二重性を持つことを前提に、新たな物理学(量子力学)を作り上げる必要があります。
あらゆる物質の二重性: 二重スリット実験では、光だけでなく、電子やフラーレン分子などのあらゆる物質も粒子性と波動性を持つことが示されています。
波動性と粒子性の二重性: 光や物質が波動性と粒子性の二重性を持つという事実が明らかになりました。ド・ブローイは、物質が波として振る舞う状態を物質波とし、その波長を計算する方法を編み出しました。
物質波の波長: ド・ブローイの式を用いて野球ボールの波長を計算すると、10の-34乗メートルという非常に小さい値になります。これはほぼゼロとみなせるレベルであり、物質の波動性が極めて小さく認識できないことがわかります。
肉眼で見える物体の波動性: 肉眼で見えるような物体の波動性はほとんどゼロであり、非常に小さな世界で初めて波動性が見えてきます。
新しい物理学の必要性: 古典力学では波動と粒子を別々に考えるため、波動性と粒子性の二重性を持つ新しい物理学(量子力学)が必要です。
シュレーディンガーの貢献: 物理学者エルヴィン・シュレーディンガーは、波動性と粒子性の二重性を持つ物質を表現するために、ギリシャ文字 Ψ を用いた関数を考えました。この関数は、電子の振る舞いを説明するために利用されます。
シュレーディンガー方程式: シュレーディンガーは波動性と粒子性の二重性を考慮し、波動方程式、粒の関係式、およびド・ブローイの物質波の式を元に、新しい関係式(シュレーディンガー方程式)を作りました。この式は波動性と粒子性の二重性を前提としています。
波動関数Ψ: シュレーディンガー方程式における波動関数Ψは、位置と時間の要素を持ちます。この式の意味を簡単に説明すると、波動関数Ψは演算子Hハットを施されたものと、定数Eを掛けたものが等しいという関係を満たさなければならない、ということです。
波動関数Ψの意味: シュレーディンガー方程式から求められる波動関数Ψとは何かを考えたとき、物理学者マックス・ボルンは、波動関数を二乗したものが、その物質が存在する確率を表しているとしました。例えば、電子の波動関数Ψを二乗することで、電子がどの場所にどれくらいの確率で存在するかを予測できます。
確率の重要性: 電子の場所を確率で表す理由は、電子が粒子性と波動性の両方を持つ存在であるため、シンプルに「ここにある」とピンポイントで考えることができないからです。量子力学では、存在をより曖昧に捉える必要があり、波動関数から導かれるのは電子が見つかる確率のみです。
反応時に位置が判明: 電子が他の物質と反応したり、ぶつかったりすることで初めてその場所がわかります。それまでは、電子の存在はあらゆる可能性が重なり合っていると考えられます。
波動関数の二乗: 波動関数Ψを二乗すると、電子の存在確率を示すグラフが得られます。縦軸は存在確率、横軸は空間座標を示し、膨らんでいる波の部分に沿って電子の存在確率が分布しています。電子が最も高い確率で存在するのは、位置$$ x = 0 $$の部分です。
確率の広がり: 電子の存在確率は空間に一点だけ存在するのではなく、広がったものとして捉えます。これにより、電子がどこに存在するのかをピンポイントで特定することはできません。
古典力学と量子力学の違い: 古典力学では、粒子の存在確率は特定の場所で100%で他の場所で0%と考えられますが、量子力学では存在確率が広がっていると考えます。これが古典力学と量子力学の大きな違いです。
波動関数の重要性: 波動関数が分かれば、電子がどの場所に何%の確率で発見されるかを計算することができます。
存在確率の計算: 例えば、Xが1から2の間に電子が見つかる確率を知りたい場合、波動関数Ψを積分して求めることができます。大体14%くらいの確率です。
量子力学の確率的考え方: 量子力学では、すべての物事を確率で考えます。物事が実際に起こる可能性は確率でしか決まっておらず、どれか一つを確率的に体験することになります。この考え方をコペンハーゲン解釈と呼びます。
二重スリット実験の理解: 波動関数を使うことで、二重スリット実験の結果を理解できます。発射される電子の波動関数Ψは、スリットAを通った状態の波動関数ΨAとスリットBを通った状態の波動関数ΨBの足し算で表されます。
状態の重ね合わせ: スリットAを通った状態の波動関数ΨAとスリットBを通った状態の波動関数ΨBが足し合わされていることを状態の重ね合わせと呼びます。これは波の性質を考えれば納得しやすいです。
電子の存在確率: 電子の位置xに存在する確率P(x)は、波動関数の絶対値の2乗で表されます。整理すると、スリットAとスリットBの状態の存在確率、およびその重ね合わせが示されます。
状態の絡み合い: 電子がスリットAとスリットBを通る可能性が同時に存在していることを示しています。これは電子が独立していないことを意味します。
確率の例: サイコロの目の出方を考えると、それぞれの目が出る確率が等しく6分の1であるように、重ね合わせの状態も確率で決まります。
干渉項: 電子の存在確率ψ²が示すように、電子がスリットAを通ることとスリットBを通ることを分けて考えることができない。干渉項が存在するため、電子の存在確率の波が干渉を起こし、干渉模様が生じます。
存在確率の波: 計算している波は存在確率の波であり、電子自体はこの確率に沿ってそのどこかで見つかる。ただし、電子自体が物理的に両方のスリットを通っているわけではありません。
観測による干渉模様の消失: スリットにセンサーを置いて電子を観測するときも、電子の波動関数を用います。センサーも量子系に影響を与えるため、センサーAが反応する場合とセンサーBが反応する場合で起こりうる事象を分けて考える必要があります。
センサーAが反応する場合: 電子がスリットAを通ると確定し、波動関数は$$ \Psi_A $$になります。これをもとにスクリーン上の電子の存在確率を計算すると、波動関数の二乗で表されます。
センサーBが反応する場合: 同様に、電子がスリットBを通ると確定し、波動関数は$$ \Psi_B $$になります。これをもとにスクリーン上の電子の存在確率を計算します。
全体の確率: センサーの反応に基づく電子の存在確率を考えると、確率の波の干渉が起こらず、スリットAとスリットB側に分布した形になります。
量子デコヒーレンス: センサーがどちらのスリットを通ったかを観測することは確率を確定させ、状態の重なり合いを壊すため、確率分布に影響を与えます。これを量子デコヒーレンスと呼びます。