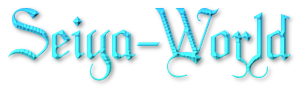はじめに
どうもSeiyaです!
IoT
IoT : Internet of Things
スマート家電の利便性: スマートエアコンを使用すれば、外出先からでもスマホで冷房をオンにして、家に着く頃には快適な温度になっているという利便性が挙げられます。また、スマートオーブンレンジがあれば、家にある食材に基づいてレシピを提案し、調理を適切に行ってくれるので、簡単においしい料理を作ることができます。
インターネットに接続された家電: パソコンやスマホだけでなく、テレビやエアコン、オーブンレンジなどもインターネットに接続できる時代になりました。このような家電を総称してIoT(Internet of Things)と呼びます。
IoTの発展: IoTが進化することで、インターネットに接続されたランドセルやバッグなど、様々な物がインターネットにつながる未来が期待されます。
IoT(Internet of Things)の利便性: メガネや洋服、靴など、さまざまなモノがインターネットにつながり、私たちの生活がより便利になります。例えば、ランドセルがインターネットにつながると、時間割や持ち物を教えてくれるだけでなく、熱中症の予防や子どもの居場所の把握が可能になります。
データの重要性: IoTデバイスが増えることで、インターネットに接続されたデバイスから大量のデータが送信されます。体温や心拍数、位置情報、音声、画像など、多様なデータが収集されます。
ビッグデータの処理: こうした膨大なデータを処理するためには、AIによるデータベースの収集と活用が重要です。データが増えることで、インターネットを通じて生活がさらに便利になる未来が期待されます。
AI(Artificial Intelligence)と健康管理: AIは膨大なデータを高速で分析し、健康管理に必要な情報を素早く見つけ出します。例えば、体調に異常があれば食事改善のアドバイスや治療が必要な場合には近くの専門医を紹介するなどの情報を提供してくれます。
IoTとAIの関係: IoTによって得られたビッグデータをAIが分析し、適切な情報を見つけ出します。これにより、AIとIoTは密接な関係を持ち、お互いに補完し合います。
AIの利便性と問題点: AIは非常に便利ですが、例えばこっそり食べたお菓子の数まで把握されてしまい、健康に悪いと止められることもあるかもしれません。
5Gインフラの重要性: IoTの進化には5Gインフラの構築が不可欠です。5Gの特徴は超高速、多数同時接続、超低遅延です。
ウェアラブルデバイスのインターネット接続: 外出時に持っていくメガネやバッグなどのウェアラブルデバイスは、自宅Wi-Fi以外のインターネットに接続する必要があります。
同時接続の問題: 多くの人がスマホでインターネットに接続しているため、特に昼間や夕方の時間帯には速度が低下します。新しいサービス(格安SIMなど)もありますが、これは余った回線を利用しているため、混雑時の速度低下が顕著です。
5Gの多数同時接続: 5Gインフラの特徴として、4Gと比較して10倍のデバイスを同時に接続できる能力があります。しかし、現時点では5Gの普及が進んでいないため、ウェアラブルデバイスはスマホの回線を共有する形になるでしょう。
スマホ経由のデータ送信: ウェアラブルデバイス(帽子、メガネ、洋服、靴など)は個別にインターネット通信するのではなく、一度スマホにデータがまとめて送られ、スマホのインターネット回線を利用してまとめてデータが送信される仕組みです。
乗り換えの中心となる空港の例: 例えば、日本からフランスに行く場合、シンガポールのチャンギ国際空港で乗り換える方が効率的です。このように、乗り換えの中心となる空港を利用することで効率が向上します。
ハブ空港の概念: ハブ空港とは、自転車の車輪の中心部分に相当し、航空路の中心的な役割を果たします。チャンギ空港はその例です。この概念をIoTデバイスの回線に置き換えると、スマホが各IoTデバイスにおけるハブの役割を果たします。
IoTの普及と課題: IoTの普及により生活が便利になりますが、回線の混雑という課題もあります。この課題を解決するためには、5Gの早期普及が望まれています。
コネクテッドカーの説明: コネクテッドカーとは、インターネットに接続された車のことで、怪しい意味は全くありません。自動運転のレベルによってクルマがしてくれることが変わります。
緊急通報システム: コネクテッドカーには、事故が発生したときにセンサーが検知して自動で警察や消防に連絡を送る緊急通報システムがあります。カーナビのGPSと連携しているため、ドライバーが動けなくても対応してくれます。
テレマティクス保険: テレマティクス保険は、車に通信システムを組み合わせたもので、走行データや運転情報を分析して保険料を算出します。運転レベルに応じて保険料が決まります。過去の事故歴や年齢、ゴールド免許の有無などを基にしていますが、テレマティクス保険はリアルタイムデータを活用します。
ペーパードライバーの問題点: 免許証を持っていても実際には運転していない人(ペーパードライバー)は、運転技術が高いわけではありません。車がインターネットに接続されることで、無意味な加速や減速、急ブレーキなどを検知して運転技術を採点できます。
保険料の適切な設定: テレマティクス保険では、リアルタイムの運転データを基に保険料を設定できます。また、常に採点されている意識があれば、安全運転を心掛けることにつながります。
盗難車両追跡システム: 車が異常を検知すると、所有者に通知が行き、GPSで車の位置を確認できます。これにより、警察に通報して早期に車を取り戻すことができます。こういったシステムがあると、車の盗難を防ぐことが期待されます。
交通事故の最大の原因: 最大の原因は不注意(確認不足や脇見運転)であり、スピード違反や飲酒運転ではありません。不注意をサポートするシステムとして、ドライバーの脈拍を感知して体調不良や眠気をアラームで知らせる機能があります。
休憩と体調管理: 休憩を取ることで事故を未然に防ぐことができますが、運転を仕事にしている人にとっては簡単ではありません。会社がIoTを利用して運転手の体調管理と車の管理を効率化することで、働きやすい環境を作ることができます。
労働環境の改善: AIが体調の悪いドライバーを見つけ出し、ビッグデータと照らし合わせることで労働環境に潜む問題を確認し、必要な改善を行います。
自動運転車の普及: 自動運転車の普及はまだ時間がかかり、完全に事故をなくすことはできません。人間と自動運転車の両方で安全が求められます。
技術の工夫: 現在の技術を活用して様々な問題に対処する工夫が必要です。インフラや法規制が整うまでの間も、ひらめき力が重要です。
便利な車の機能: 安心安全のためのシステムだけでなく、暮らしを便利にする機能もあります。例えば、パーキングアシストシステムや、スマホアプリで車の状況を確認する機能などがあります。
スマート操作: スマホから車のライトを消したり、GPSで車の位置を確認できる機能が既に実用化されています。
車両点検: スマホのアプリを使ってタイヤの摩耗やエンジンオイルの状態などの車両点検が可能です。
キャッシュレス決済の進展: クレジットカード、モバイル決済、電子マネーなどのキャッシュレス決済が普及しています。QRコード決済もその一部であり、インターネットを利用してデータを送受信しています。
セキュリティ対策: QRコード決済の不正利用を防ぐため、QRコードの画像は短時間しか利用できないように設定されています。また、2段階認証が導入されており、セキュリティが強化されています。
具体例: 例えば、セブンイレブンが2019年に導入したスマホ決済サービス「7Pay」は、不正アクセスにより約5500万円の被害が発生しました。こうした事件を受けて、セキュリティ対策が求められています。
ブルートフォースアタックと2段階認証: コンピューターで自動的にランダムなIDとパスワードを生成し、総当たりでログインを試みるプログラムをブルートフォースアタックと呼びます。これを防ぐために、IDとパスワードが一致した後、登録したスマホに短い制限時間内に入力する4桁のパスワードを送る2段階認証が使用されます。
キャッシュレス決済の普及状況: 日本では現金主義が強く、キャッシュレス決済の割合は約25%程度です。一方、主要国ではキャッシュレス決済が40%から60%程度普及しており、韓国では96%を超えています。
デジタル人民元: 中国では、通貨をデジタル化するデジタル人民元の運用が進んでいます。これにより、現金の偽札問題が解決され、キャッシュレス決済が普及しました。
東京オリンピックの影響: 2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックに向けて、海外の観光客が日本で気軽にお金を使えるよう、キャッシュレス決済の環境整備が進められました。
キャッシュレス決済の利便性: キャッシュレス決済は、自動で通貨の交換ができるため、外国人が両替の手間なく買い物ができます。
スーパーやコンビニの人手不足: IoTショッピングカートが開発されており、買い物かご自体がレジの役割を果たし、金額を計算するなどの機能があります。
ネット注文の増加と配送ドライバー不足: ネット注文が増えることで、配送ドライバーが不足するという問題が出てきます。この問題を解消するために、ドローン配送が期待されています。
ドローン配送の課題: ドローン配送には、重いものを運ぶパワーや耐久性、安全なルート管理、事故回避システムなど、まだ多くの課題があります。
ホテル業界におけるIoT技術の活用:
- ホテル不足問題に対処するため、スマートホテルが期待されている。
- 部屋の空調や照明、チェックイン・チェックアウトなどをスマホで操作できるシステムが導入されている。
- 世界初のロボットが働くホテルも存在し、受付や荷物預かり、バーでの飲み物提供をロボットが行う。
レストラン業界におけるIoT技術の活用:
- タブレットを利用した注文システムが普及し、オーダーミスを防ぎ、業務を効率化。
- 業務の効率化によって人手不足の解消に貢献。
容器おもてなしクラウド:
観光地やホテル、交通機関の情報を旅行者の言語に変換して提供し、スムーズな旅行体験を支援。
日本のアニメカルチャーとおもてなし:
- 案内役のビジュアルや声を好きなキャラクターに変えるアプリがありそう。
- 日本のアニメは世界的に人気があり、ユーモアを取り入れたおもてなしが重要。
IoT技術の事例と共通点:
買い物やレストランでの人手不足問題を解決。
すべての事例において、何かを解決している。
キャッシュレス決済で生活が便利になり、経理作業の時間を削減。
- ホテル業界の人手不足問題: IoT技術を利用してスマートホテルの導入が期待されています。
- スマートフォン操作での機能: 部屋の空調、照明、チェックイン・チェックアウトなど、ほとんどのホテルの機能をスマートフォンで操作できるようになるシステム。
- ロボットホテル: 世界初のロボットが働くホテルがあり、受付から荷物の預かり、バーでの飲み物提供までロボットが行っています。
- レストランの効率化: タブレットを利用した注文システムで、オーダーミスを防ぎ、業務を効率化し、人手不足の解消に貢献。
ホテル業界におけるIoT技術の活用:
- ホテル不足問題に対処するため、スマートホテルが期待されている。
- 部屋の空調や照明、チェックイン・チェックアウトなどをスマホで操作できるシステムが導入されている。
- 世界初のロボットが働くホテルも存在し、受付や荷物預かり、バーでの飲み物提供をロボットが行う。
レストラン業界におけるIoT技術の活用:
- タブレットを利用した注文システムが普及し、オーダーミスを防ぎ、業務を効率化。
- 業務の効率化によって人手不足の解消に貢献。
容器おもてなしクラウド:
- 日本に来た外国人旅行者に、観光地やサービスをお勧めする仕組み。
- ビッグデータを活用し、旅行者の国、性別、年齢に基づいて最適なサービスを提供。
- 観光地やホテル、交通機関の情報を旅行者の言語に変換して提供し、スムーズな旅行体験を支援。
日本のアニメカルチャーとおもてなし:
- 案内役のビジュアルや声を好きなキャラクターに変えるアプリがありそう。
- 日本のアニメは世界的に人気があり、ユーモアを取り入れたおもてなしが重要。
IoT技術の事例と共通点:
- すべての事例において、何かを解決している。
- キャッシュレス決済で生活が便利になり、経理作業の時間を削減。
- 買い物やレストランでの人手不足問題を解決。
のぞみプログラミング&Webスクール:
- 子供向けのプログラミングスクール。
- 教育系ジャンルの情報を毎週定期的にアップ。
- チャンネル登録を推奨。
IoT技術と医療の変革:
- ポスペタルト: 病院で使用されるIoT技術を活用したシステム。スマートフォンやタブレットを利用して、病院と患者を結ぶ。
- 地方の医療問題: 都会に医者が集中し、地方では医者が少ない。オンライン診療が注目されており、患者が遠隔地から専門医に診てもらうことができる。
- オンライン診療のメリット: 家にある機械を通じて、体温や血圧などのデータをリアルタイムで監視。異常があった場合にはすぐに対応可能。AIが24時間健康データを見守り、家族やヘルパーの負担を軽減。
- 医療データの共有: 患者の医療データを共有することで、複数の医者が一人の患者を診ることができる。現在は紹介状やおくすり手帳が必要だが、データ共有によって手間が省ける。
予防医療の重要性:
- 予防医療の考え方: 病気になる前に異変を発見し、未然に防ぐこと。
- 健康を意識した生活習慣: ウォーキングや身体を鍛えること、サプリメントで栄養補給することも予防医学の一環。
IoT技術の役割:
- スマートトイレ: トイレでの排泄物を分析し、健康状態をチェック。糖尿病や腎臓病などの病気を早期に発見。
- ビッグデータの活用: 健康な人のデータも含めて大量のデータを収集し、病気のリスクを高精度で分析。
日常生活でのセンサー活用:
- 身体に貼るタイプのセンサー: 心拍数、脳波、筋電図、体温などのデータをリアルタイムに測定し、健康チェックが可能。
予防医療の重要性:
- 予防医療の考え方: 病気になる前に異変を発見し、未然に防ぐこと。
- 健康を意識した生活習慣: ウォーキングや体を鍛えること、サプリメントで栄養補給することも予防医学の一環。
IoT技術の役割:
- スマートトイレ: トイレでの排泄物を分析し、健康状態をチェック。糖尿病や腎臓病などの病気を早期に発見。
- ビッグデータの活用: 健康な人のデータも含めて大量のデータを収集し、病気のリスクを高精度で分析。
日常生活でのセンサー活用:
- 身体に貼るタイプのセンサー: 心拍数、脳波、筋電図、体温などのデータをリアルタイムに測定し、健康チェックが可能。
診療データの共有:
- 過去の診療データを参照し、適切な治療や薬を提供することで、均等な医療を実現。
手術のサポート:
- 手術中の医療機器から得た情報をAIが分析し、最適な手術法を提供。
AIの活用:
- 患者の体温や心拍数、血液の状態などから最適な治療法を見つけ、手術の成功確率を向上。
IoTに使われる新しい通信方式:
- 5Gの特徴: 超高速で安定した通信。ただし、電波の届く距離が短く、建物の壁や雨で電波が弱くなる。
- LPWA(省電力広域通信): 少ない電力で広範囲に通信できる。バッテリーが長持ちし、電源の届かない場所や小さなセンサーに適している。
- 事例: 公園や畑の管理、メーターの自動チェック。
- メリット: 基地局の設置数を減らし、低コストで運用可能。通信速度は遅いが、必要なデータ量が少ないため問題ない。
LPWAの利点:
- 低電力消費: 一般的に売られているバッテリーで数年持つ。手間がかからない。
- 広い通信範囲: 最大で約50kmの距離をカバー。
- 低コスト: 通信量が少ないため、通信コストを抑えられる。例えば、月10円で利用可能。
以下に要約しました:
Society 5.0とIoTの関係:
- Society 5.0の特徴: 人間中心の社会で、ビッグデータやAIを活用して経済発展と社会問題の解決を目指す。
- 過去の社会の進化:
- Society 1.0: 狩猟社会(原始時代)
- Society 2.0: 農耕社会(農業の発展)
- Society 3.0: 工業社会(産業革命)
- Society 4.0: 情報化社会(インターネットやスマートフォンの普及)
現在の課題とIoTの役割:
- 高齢化社会問題: 労働者人口の減少と人手不足を解決するため、IoTとAIを活用して労働の効率化を図る。
- エネルギー効率の向上: IoTの活用によって、利用するエネルギーを少なくし、無駄な電気を減らす。
具体例:
- 農業: ドローンや水分センサーを活用して効率的な農作業を実現。
- 家庭: 食材の自動注文やレシピ提案で家事の時間を減少。